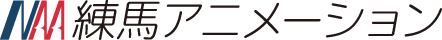第16回:堀川和政氏(東映アニメーション)のアニメ「履歴書」《その1》
思い起こせば37年前の大学卒業を3月に控えた頃、「いつから会社の方に来れる? 早めに来れる?」という話の流れで、東映動画に勤め始めたのが昭和57年2月14日。なぜ、この日に決めたかの記憶はなく、その日がバレンタインの日であったため、日付だけは忘れたことがない。それが、特に長く勤めると決心して始めたわけではないが、結果として一度も辞めることなく、ひとつの会社で勤め上げることになった東映動画人生始まりの日である。大学の同期であり、月岡貞夫さんの授業を共に受けた仲である佐藤順一は、東映動画が芸術職の採用を久しぶりに再開した前年4月に、東映動画第1期研修生として、大学を中退して既に就職、演出助手としての道をスタートしていた。一方、私は卒業してから会社人生をスタートしたのだが、その年、東映動画で研修生の採用はなかったため、第1期・影の研修生という位置付けで、その後の人生を歩むことになった。卒業制作でコンテ、演出から作画、仕上、背景、撮影、音楽まで全てを自作した5分ほどのアニメ作品を評価して頂いての演出助手としての採用である。
最初の仕事=最初についた作品は「FUTURE WAR 198X年」という劇場作品。実写で地位のある舛田利雄と宇宙戦艦ヤマトで共に作品を世に知らしめた勝間田具治の2人の巨匠が監督を務め、ポスターデザインに生頼範義(スターウォーズのポスターデザインで有名)を起用するなどした超ビッグな作品。私はこの作品の製作進行に付き、アニメの製作人生の一歩を踏み出したのである(演出助手としての採用ながら、当時は製作進行から始めるのが通例であった)。
この作品の製作担当は、後に東映アニメーションの専務となるMさん。その人の下に付いたわけであるが、勤務初日から夜10時過ぎの帰宅。こちらは何も分からない身であったし、無心に一所懸命やっていたので、長時間働かされているという受け止め方ではなかったが、Mさんと同じ屋根の下、製作部で仕事をしていく中で、この人の作品の作り方(スケジュールを引っ張れるところまで引っ張る)により、しなくていい苦労も数知れず、逆に大いに学ばせて頂いた。よく言えば、少しでも仕上りのいい作品を作る。悪く言えば、締めるところで締められずルーズこの上ない、という作り方である。大学の卒業式の日も朝から夜遅くまで働き、製作終盤は休みなく朝帰り、徹夜も当たり前の勤務を続けた。そして、ついに作品は完成。ひとつやり遂げたという感覚と、初号試写会で自分の名前が載ったエンディングを目にし上映が終わった時の充足感は、それまで大変だったことなど吹っ飛ばし、晴れやかな気分、心に澄んだ青空が一面に広がるような感覚をもたらしてくれた。その感覚は、この作品以降も、製作に携わり作品が完成し初号試写を見るたびに味わう感覚である。その後も、自己中な監督やアニメーター、クソみたいな上司、スタッフがいる中で、常にスケジュールが厳しく、明るいうちに帰ったこともなく、休みも満足にない中で、アニメ製作の仕事を続けてしまったのは、作品を作り終えた時の充足感があったからに他ならない。それも作品製作の全工程に関与する製作進行や演出助手、演出という仕事だったからこそ、より一層強い充足感を得られたのだと思う。
影の研修生としてスタートした身分が影響したのかは定かでないが、最初に劇場作品につくと、その後自分に振り当てられる作品はビデオ作品や単発ものが中心であった。佐藤順一をはじめ他の研修生はテレビシリーズ作品が中心の配置であったため、仕事のローテーションが短いサイクルで回り、エンディングに名前が載るのも頻繁で、作品タイトルのメジャー感や華やかさも感じられたので、結構羨ましく思っていた。そんな境遇の中でも楽しかったのは、夕方5時に終業チャイムが鳴り、昼間の仕事が一区切りしたところで夕食を取り、もうひと仕事、夜の仕事にかかる前に、大会議室の隅に折りたたんで置かれている卓球台をフロア中央に移動、設置し、同期の仲間(第1期研修生や同時期入社の同年齢の演出助手や製作進行)3~4人で小1時間ほど卓球をした時間である。絶好の息抜き、気分転換には打ってつけであったし、その後公私で付き合う中で、個々の性格の悪さやエゴの強さにうんざりして距離を置くようになった人間関係を思えば、入社したての時期だからこそ成立し得る、会社青春時代の思い出である。現在ではありえない、当時だから許された働き方であったとも言える。ちなみに当時は、演出に原画チェックをのんびり(というか、じっくり)やる方がいて、S川さんなどは夜に自席で酒を飲みながら原画チェックをし、原画がなっていないと演助や進行を捕まえては、とうとうと演出論を話し始める有様。そんな個性豊かといえばそれまでだが、付き合う側からしたら「もういい加減にして、勘弁してよ、あんたのチェックの後、仕事をする我々の身にもなってよ」と言いたくなるような、ある意味、大らかな時代だったと思う。
それから数年後、東映動画製作部が長年に渡り人の採用を行ってこなかった影響で年長者が増える一方の現場であったが、ようやく第1期研修生を中心とした若い活気に満ちた会社に変貌しつつもあった。彼らが作品製作の中心的な位置を占めるようになってきたわけであるが、私も周回遅れながら演助進行として東映動画製作部のテレビシリーズ作品を回す一員となっていた(その頃の製作体制では、演出助手と製作進行は一人二役で演助進行としてテレビシリーズを3人で回すのが定番であった。その後、会社は演出助手で募集しておきながら、進行もやらせるのは問題ではないかという社内理論が強まり、兼務が取り止めになった)。
次回は、演助進行から演出を経て、製作管理に至った経緯と「デジタル製作プロジェクト」について、お話しします。
堀川和政(東映アニメーション)